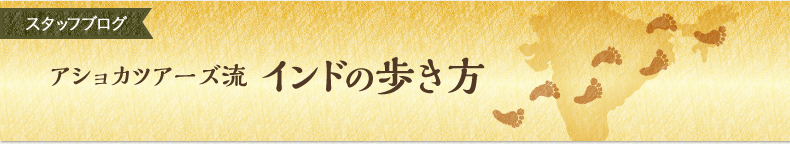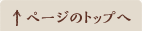あなたとインド・南アジアをつなぐ旅行会社
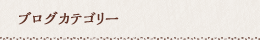
- TOPICS (124)
- ツアーについて (63)
- 乗り物・交通 (8)
- 現地係員(エスコート) (6)
- ホテル (2)
- 気候・服装 (7)
- ご注意 (10)
- お金のこと (6)
- お客さまの声*アンケート (25)
- スタッフ紹介 (3)
- インド・ネパール観光名所 (45)
- 北部(デリー近辺) (5)
- 仏教遺跡 (30)
- お釈迦様ゆかりの聖地 (25)
- 仏教ゆかりの地 (7)
- 西部(ムンバイ近辺) (5)
- 仏教美術 (3)
- 旅の準備 (16)
- 持ち物・必需品 (7)
- パスポート・ビザ (5)
- 航空券の手配 (2)
- スーツケース・かばん (3)
- インドあれこれ (107)
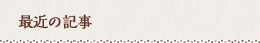
- 2024年4月19日
- ゴールデンウィーク期間中の営業について
- 2024年4月3日
- 【添乗員同行ツアー】2025年2月19日発 インド仏蹟巡礼の旅 9日間(JAL直行便)
- 2024年4月2日
- 【お待たせいたしました!】山本高樹さんとインドの秘境をいく 2024夏ツアー発表
- 2024年2月9日
- 【イベントのお知らせ】ラダック旅遊フェスタ 2024 @東京 (イベント終了)
- 2023年5月17日
- ●Newツアーのご案内● スリランカ アーユルヴェーダのツアー
- 2023年4月28日
- 日本入国時の検疫措置(水際対策)の緩和について
- 2023年4月10日
- 【空港・仏跡聖地レポート】3年ぶりにインド添乗にいってきました。
- 2023年3月13日
- アショカツアーズ営業再開のお知らせ (2023年4月3日〜)
- 2022年11月24日
- ★インド旅行に向けての朗報★ インド入国前のエアスビダ登録が不要に
- 2022年9月6日
- 《9月7日(水) 20時配信》ブダガヤよりオンライン無料配信します
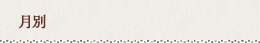

- トップ
- アショカツアーズ流インドの歩き方
仏教ゆかりの地の記事一覧
【添乗員同行ツアー】2025年2月19日発 インド仏蹟巡礼の旅 9日間(JAL直行便)
2024年04月03日 15:25
釈尊の生涯と教えを学ぶ インド仏蹟巡礼の旅を、駒澤大学名誉教授 皆川廣義先生監修のもと企画させていただきました。
6名様以上のご参加で日本より添乗員が同行いたします。
この機会に心の旅をされてみてはいかがでしょう。
● 詳しくはこちらをご覧ください → インド仏蹟巡礼の旅 9日間(JAL直行便利用)


ツアーお問い合わせ先:(株)ビーエス観光 東京営業本部 アショカツアーズ
TEL: 03-3502-4022
FAX: 03-3502-5416
email: tokyo@ashoka.co.jp
担当: 唐沢(範)
【お釈迦様涅槃の地、クシナガラに国際空港が開港しました】
2021年10月21日 11:48


考古学博物館 サールナート出土品を展示
2015年01月13日 10:13

サールナート遺跡のすぐ近くに、出土品を収蔵する考古学博物館が建っています。小規模ながらインド第一級の文化財が展示されており、一見の価値ありです。
■【柱頭四頭獅子像】

遺跡エリアに残るアショカ王柱の上部に載せられていた彫刻が、博物館の入口正面に展示されています。マウリヤ王朝期の作品で、博物館内では最古の彫刻作品です。下部には「蓮弁」があり、その上に「獅子-法輪-象-法輪-牛-法輪-馬-法輪」が彫刻されています。
この像が表すものには、それぞれに意味や由来があります。
四方を向いた4頭の獅子・・・『世界中にあまなく仏教が広がるように』という念願
法輪・・・お釈迦様の最初の説法(初転法輪)
四大聖獣
獅子・・・お釈迦様には「釈迦族の獅子」の異名があった
象・・・マヤ夫人がお釈迦様を懐妊されるとき白象の夢をみた
牛・・・お釈迦様の「ゴータマ」という名前には「最良の牛」という意味があった
馬・・・お釈迦様の出家は馬に乗って行われた
インドの国宝の中でも最も重要な作品で、インド政府の国章ともなっています。お札にも印刷されています。

■【転法輪印仏陀坐像(初転法輪像)】
ガンダーラ・マトゥーラで1世紀頃考案された仏像は、5世紀を中心としたグプタ王朝の時代に、最も洗練された様式美を完成させました。その中の最高傑作の1つが、サルナートから出土し、考古学博物館の左館の一番奥に収蔵される転法輪印仏陀坐像でしょう。(写真は、ムラガンダクーティ寺院内に奉られたレプリカです。)

お釈迦様の「初転法輪」を表す像で、その表情は端正で慈愛に満ちています。大型の光背の上部には“飛天”が刻まれ、光背の下の両脇には“伝説の魚マカラ”、その下には“有翼の獅子レオ・グリュフ”が表現されます。印相(手の形)は「転法輪印」を組み、台座の中央には“法輪”、両脇に“五比丘”、“初転法輪を五比丘とともに聞いた鹿”が表現されています。“左端の女性と子供”はこの作品を寄進した在家の親子だと考えられます。
その他、仏陀や神々の像、仏教説話のレリーフなど、さまざまな彫刻が展示されています。




入口でX線検査を受けて入場します。館内は写真撮影禁止で、カメラやビデオなどの撮影機器は一切、持ち込めません。

※当社企画ツアーでは、サールナートを訪れる日が休館日(金曜)にあたる場合、ご見学いただけません。
<<< サールナートを訪れるツアーはこちら >>>
ムーラガンダクティ寺院 野生司香雪の壁画
2015年01月13日 10:11

サルナートでの初転法輪の後、お釈迦様はラジギールと祇園精舎を拠点にされ、世に仏法をお広めになりました。そして何世紀もの年月をかけ、スリランカやタイ、中国、韓国、日本へと伝えられました。仏教は、インド国内では衰退してしまった一方で、外国ではそれぞれの国や民族の文化にあわせて形は変わりつつも根付いています。サールナートは今日、インドだけでなく世界中の仏教徒にとって大切な聖地となっています。
-----------------------------

スリランカ人僧侶ダルマパーラ師は、初転法輪の地・サルナートに再び祈りの場をつくろうと「マハボディ・ササエティー」を組織し、1931年に寺院を建立しました。入口直上に、日本仏教連合会から寄進された梵鐘が吊るされ、清水寺管長であった大西良慶師による文字が記されています。そして内部の壁面には、日本人画家、野生司香雪(のうすこうせつ)による、お釈迦様の生涯がテーマの躍動感溢れる壁画が描かれています。
~野生司香雪(のうす こうせつ)画伯~香川県出身の日本画家、父は浄土真宗の僧侶。東京美術学校(現東京芸大)卒、長野善光寺の雲上殿壁画(昭和22年)を手掛けました。アジャンタ壁画の模写を手伝った経歴(大正6年)と、詩人タゴールと交流が縁で、昭和7年に、サルナートのムラガンダクティ寺院に派遣され、お釈迦様の一生の壁画を描きました。(1885-1973)
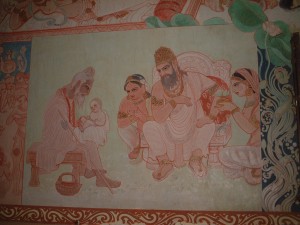

寺院横には「初転法輪を行うお釈迦様と五比丘」の像があり、菩提樹の大木が茂ります。この樹は、寺院落慶の際に、スリランカ・アヌダラプーラの「スリマハ菩提樹」から株分けされたもので、ブダガヤの金剛宝座の上に茂る聖木の“兄弟”にあたります。


<<< ムーラガンダクティ寺院を訪れるツアーはこちら >>>
ニガリーハワー 前世の過去仏の誕生地
2014年12月28日 10:00

古代の仏教では『お釈迦様が悟りを開いたのは、前世である「過去仏」の功徳が累積した結果』と考え、お釈迦様のみでなく、過去仏も礼拝の対象として重要視されました。これは仏教の根本理論の一つである「輪廻転生」の考え方で、『前世の功徳が大きさにより、来世が決定づけられる』という思想によります。
「釈迦の前世の過去仏」とは、以下の七仏です。(「七仏」にはお釈迦様も含まれるため、前世は「六仏」です。)
① 毘婆尸佛(ビバシブツ)
② 尸棄佛(シキブツ)
③ 毘舎浮佛(ビシャブツ)
④ 倶留孫佛(クルソンブツ)
⑤ 倶那含牟尼佛(クナゴンムニブツ)
⑥ 迦葉佛(カショウブツ)
⑦ 釈迦牟尼仏(シャカミニブツ)
ティラウラコットの北東5.5㎞に位置するニガリーハワーは、第5仏「倶那含牟尼佛」生誕の地とされ、アショカ王柱が建てられました。現存する2本の内1本の碑文には、『ピヤダシ王(=アショカ王)は戴冠14年を記念して、倶那含牟尼佛のストゥーパーを拡大し、戴冠20年を記念に敬意を払い石柱を建立した』と刻まれています。なお、横たわる石柱に残るチベット文字と孔雀の彫刻は、後世に刻まれたものです。
※ニガリーハワーへの道は整備がされておらず、道路の損壊や雨期の冠水により、たどり着けない場合があります。